皆さん読書はしていますか?
読書をされている方なら、
一度は通る疑問があると思います。
それは、
「自分の読書の方法が正しいのか?」
というものです。
私は読書は好きですが、
果たして効果的に読めているのか
いまいち自信がありません。
そこで、本書のタイトルに惹かれました。
「自分の頭で考える読書」
”本の内容を鵜呑みにしがち”
”深みのある読解が出来ていない”
そんな悩みを持つ私にぴったりだと
思いました。
本書では具体的な読書術は
説明されません。
それより更に抽象度の高い
”本とどうつきあっていくか?”
という視点で話が展開されていきます。
それでは本の紹介を始めたいと思います。
『自分の頭で考える読書』の概要
この本はこんな人におススメです。
『自分の頭で考える読書』から学んだこと、心に残ったこと
そもそも、本の魅力って何?

読書の方法について入っていく前に
皆さんに聞いてみたいことがあります。
それは、
「本の魅力ってそもそも何?」
ということです。
情報を得たいのであれば、
今ではテレビやネットがあります。
情報を得ることのできるスピードでいえば、
本は上記のメディアに対して、
大きく劣っています。
さてそう考えた時に本が持つ魅力とは
何でしょうか。
その一つに
「思考することのできる余白がある」
ということが挙げられます。
テレビやネットで入ってくる情報は、
動画や音楽といった非常に「圧」の強い情報です。
言い換えるなら刺激が強い情報ともいえるでしょうか。
なので我々は、情報を受け取るのに
精一杯になってしまいます。
そうして、得た情報を鵜呑みに
するようになってしまうのです。
一方で本は、あるとしても多少の
挿絵や画像程度です。
刺激の弱い情報なので、
自分の考えを挟む余地が
出来るのです。
そうすることで、自分の考えを
深めていくことができるという
メリットが本にはあるのです。
本は情報の「圧」が弱い為、考えを深めることの出来る「余白」がある。
ではどんな本を読むべきか?
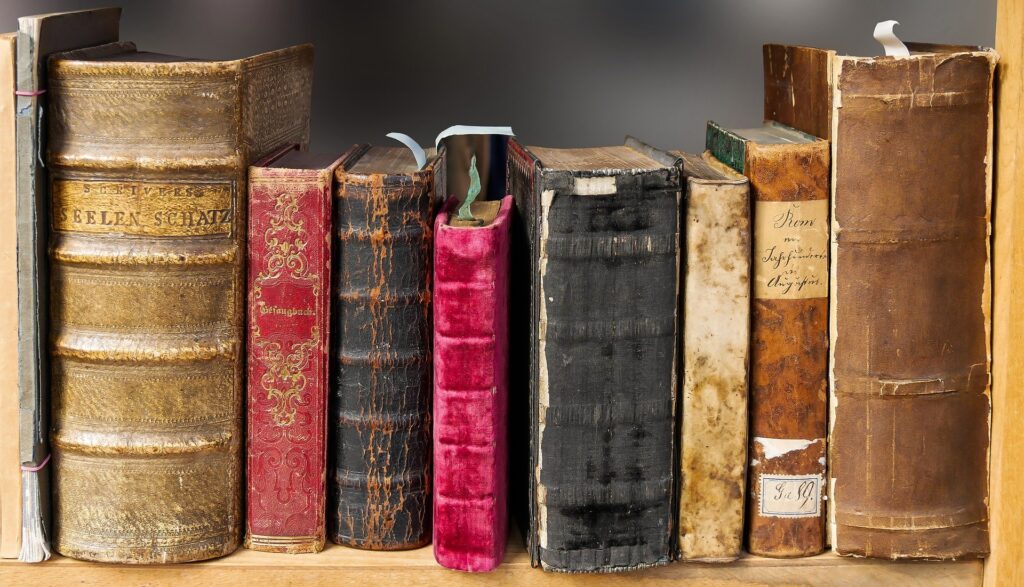
”好きな本を選んでいたら、
似たようなものばかりになってしまった。”
こんな経験は皆さんありませんか?
私は、特に自己啓発本でこの現象に陥ります(笑)
もちろん本は好きな本を読めば
いいと思います。
しかし、偏りなく本を選ぶにはどうしたら
よいのでしょうか?
そこでヒントになるのが
以下の分類法です。
①新たな「問い」を発見できる本
②新たな「答え」を発見できる本
➂既に知っている「問い」と「答え」を再確認する本
①は、そもそも自分が思いもしなかった「問い」を与えてくれる本です。
例えば
「人はなぜ他者とコミュニケーションがとれるのか?」
「心とは何か?」
当たり前に思っていて、そもそも疑問に
思わなかったこと。
ここの対して、疑問を与えてくれる、「問い」
与えてくれる本が①になります。
②は「問い」は持っていたが、「答え」を知らなかった
もしくは、新しい「答え」を得ることができる本です。
③は既に知っていることについて、
改めて学び直す本です。
既にある知識を、強化するイメージです。
こう本を分類すると、皆さんは自分の読んでいる本が、
特定の分野に偏っていないでしょうか?
自分の場合は圧倒的に③が多かったです。
既に知っていることについて書かれた本を
なぜかよく読んでました・・・
上記のように、分類して、読書をしていくことで
よく広く、深く知識を育てていくことができます。
ぜひトライしてみてください。
本をカテゴリー分けすることで、自分の持っている本が
偏っていないか客観的に把握できる。
ではどう読むか?

「具体化と抽象化」
これを一つの読み方として、著者は紹介しています。
例えば、ラグビーに書かれた本を
読んだとしましょう。
この本を「ラグビーに関する本」として読んだ人は、
それ以上に本の内容を生かすことができません。
この本が生きるときは、自身がラグビーをする時や
ラグビーを見るときでしょう。
一方でこの本を、一段階抽象度を上げて
「チームプレーをするスポーツ」として読むと
どうでしょうか。
この本の内容は、同じチームプレーをする
サッカーや野球にも当てはめることができます。
またスポーツだけでなく、同じチームプレーである
仕事などにも生かすことが出来るかもしれません。
これが、具体から抽象へのジャンプです。
逆に抽象から具体は、そのままですね。
抽象的な内容を実際の事例に当てはめて、
考えてみることです。
こうすることで、
「読んだけど、結局現実世界では役に立てることができない」
といった事態を避けることが出来ます。
本を読むときは、具体化と抽象化を意識
まとめ 本の内容を実践してみて

紹介した、本の分類方法をした結果
自分の持っている本が如何に偏っているか
わかりました。
知っていることを、何回も
学び直しているのです(笑)
人は自分の考えと同じことが書かれている
本を好んでよむんでしょうね。
(自分の考えが正しいと安心するためでしょうか・・・?)
なので、本を分類したことは、
自分の知識の偏りに気づけたので
よかったです。
また「具体化と抽象化」について。
本書の中で著者が言っていますが
人によってどちらが得意か分かれるそう。
ちなみに私は圧倒的に「具体化」人間。
抽象化を意識して読んでみると
視野が広くなる気がしました。
ちなみに抽象化する際に便利な
フレーズが「つまり」です。
(反対に具体化したいときは「例えば」です)
このフレーズを意識して読むだけでも、
今までの自己流の読書が、多少良くなったと
思います。
ぜひ皆さんも、本書を読んで
読書スキルをレベルアップさせていきましょう。

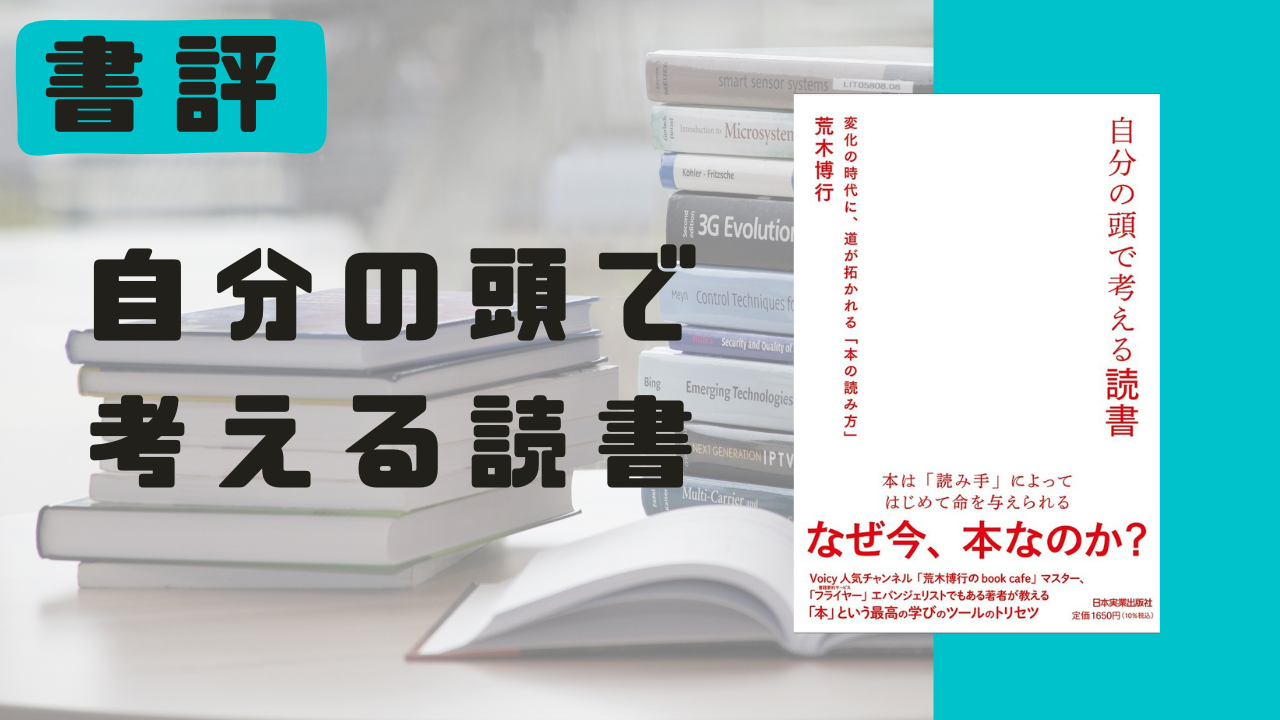
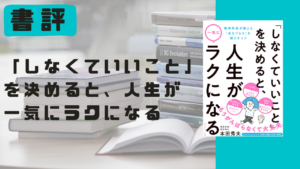

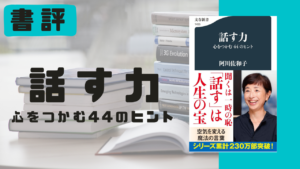
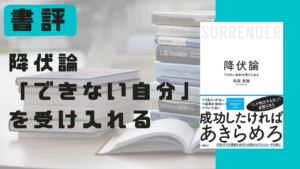
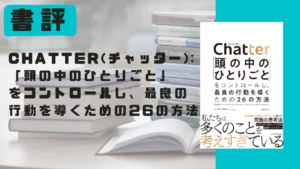
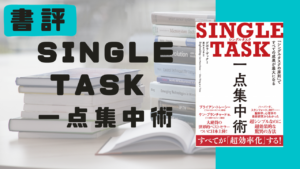
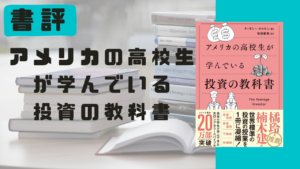
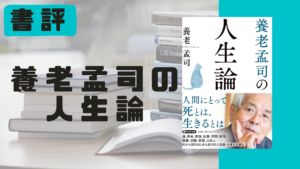
コメント